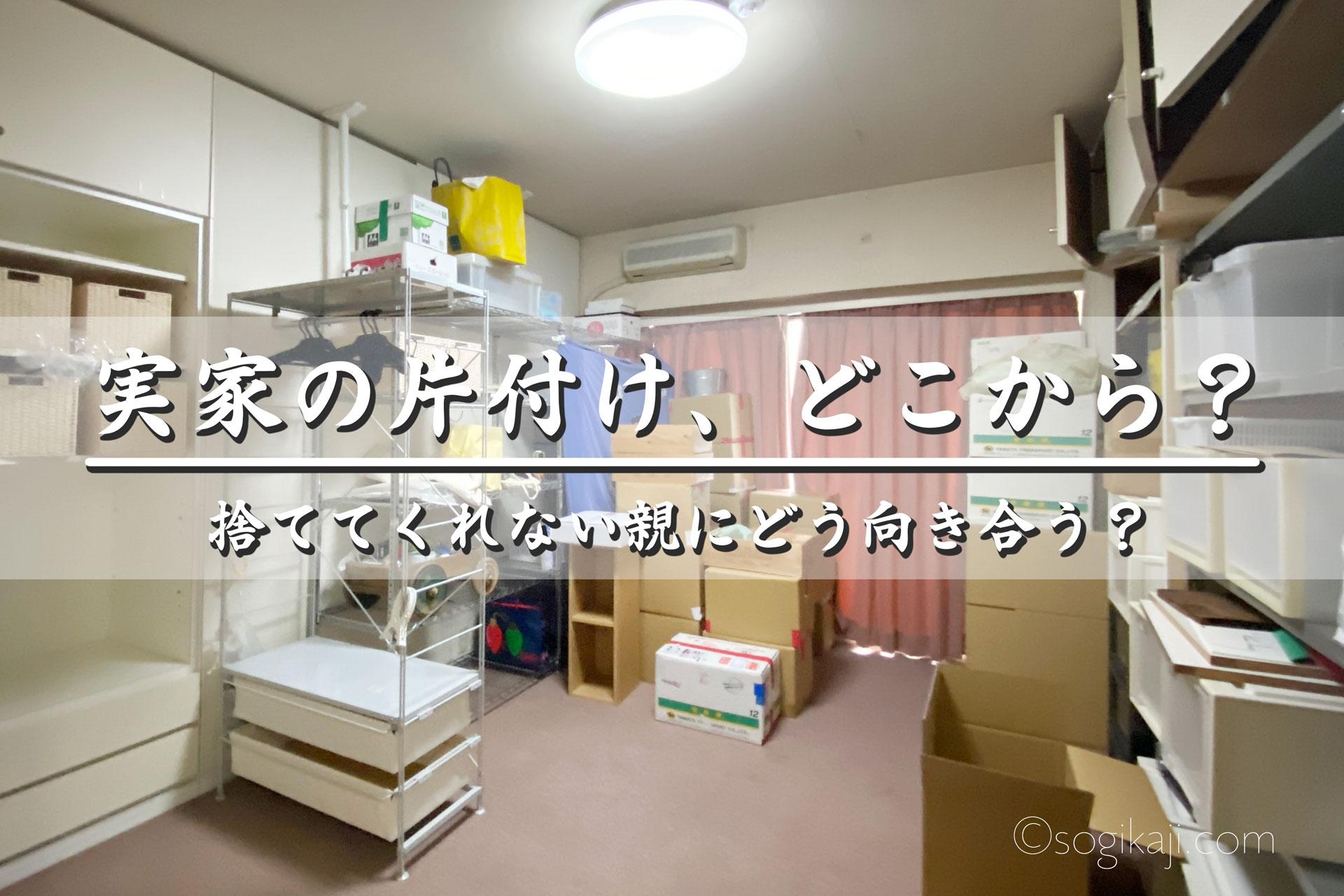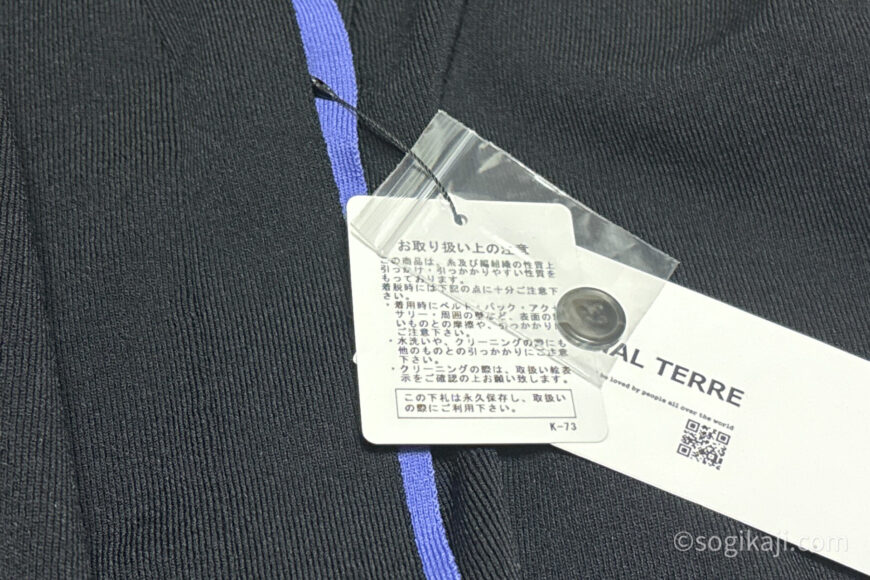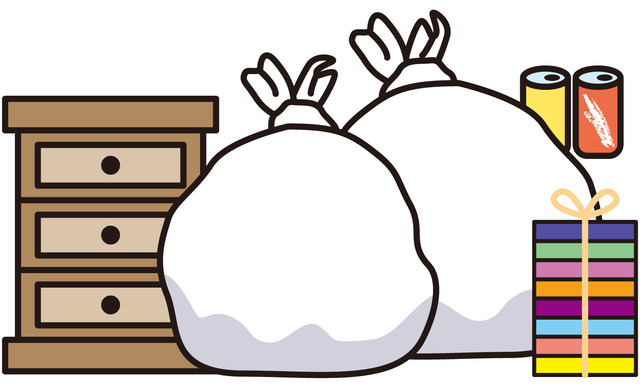実家の片付けをしようとした時に、まずぶつかる壁。
それが「親が捨ててくれない」問題です。
私の親も、もったいない精神がとても強いタイプ。
でも、その親である祖父は、実はミニマリストでした。

このギャップ、面白いですよね。
実際、この矛盾が“片付けが進まない家庭あるある”だったりします。
捨てる=悪?でも、本当にもったいないのは…
「まだ使えるのに捨てるなんて、もったいない」
そう言って、たくさんのモノが実家に溜まりがちです。
でも私は思うのです。
家って、人生で一番高い買い物。(家賃だって高いですよね?)
その空間を活かせずにモノで埋もれてる方が、よっぽどもったいない。
本当に必要な空間を圧迫してまで“いつか使うかも”を取っておくのは、未来を塞いでしまう選択。
使わないモノがあることで、掃除がしづらい・転びやすい・探しものが見つからない…。
日常生活が不便になるほうが、ずっと損なんです。

捨てないことで、反省ができなくなる
• 使い切ったと思えたら、心置きなく手放せる
• でも、使い切れていないと、「捨てるのはもったいない」と思ってしまう
• 捨てないと、自分が買った“失敗”を直視できない
…こうして、また同じようなモノを買ってしまう。
負のループです。
だからこそ、今ある「使ってないけど捨てられないモノ」を手放すことは、次にモノを買う時の戒めになります。

親のモノを勝手に捨てるのはNG
片付けの基本は「今使っているモノだけを残すこと」。
でも、それが通用するのは“自分のモノ”だけ。
親世代は、「持っていること」に安心感を感じる人が多い。
そして、そのモノたちには思い出も詰まっている。
どんなに古くてダサく見えても、勝手に捨てるのは絶対にダメ。
子ども側が「これは不要でしょ」と判断しても、親にとっては大切な存在かもしれません。
「捨てられない親」との片付けで大事な視点
親と一緒に実家を片付けるとき、いちばん大切なのは…
子ども側が「必要・不要」を把握しておくこと
親が捨てたくないというなら、今のところは把握しておくだけです。
いずれ親が亡くなってしまったとき。
その時に、何が重要で何が不要なのかが分からないと、片付けが本当に大変になります。
そして、もっと厄介なのが、
今は“ゴミのように見えていたもの”が、
親が亡くなった途端に“思い出”になってしまうこと。
感情が邪魔をして、子ども側もモノが捨てられなくなってしまう。
だからこそ、“今のうちに子世代の目で不要だと判断できるモノ”は、『いつかその時が来たら開梱せずに捨てるモノ』として分類しておくことが有効です。
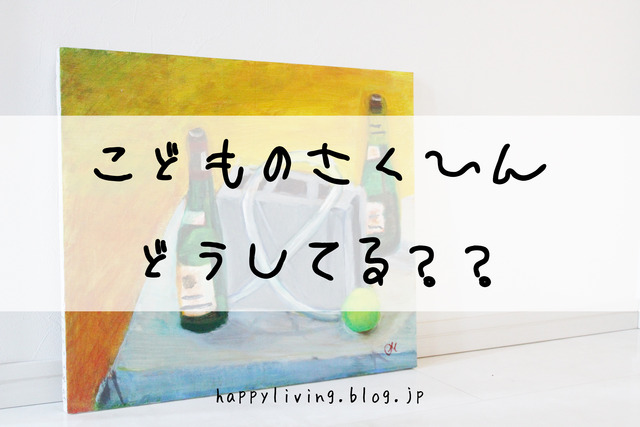
ゴミを思い出として掘り返さない
親が捨てられないモノ。
子世代の目から見れば、「これはどう見てももう使わないでしょ…」というモノ。
でも、親がどうしても捨てられないなら、それはそれでOK。
そんな時は、こう提案してみてください。
「これは残しておこう、でも、ここになくても良いよね?」
将来見なくても処分できるように、分類しておく。
本当はもう必要ない。でも、親は取っておきたい…
持ち続けていれば安心できるモノは、今の生活スペースを圧迫しないように、まとめて普段使わない部屋に積み重ねておけばOK。
2階でも物置でも、トランクルームを借りるのもアリです。
90%取り出したくなることはないので、取り出しにくくて良いのです。
なるべくスペースを取らないように邪魔にならない場所に詰め込んで詰め込んでおく。
そして、そのケースには 「〇〇年にまとめたもの」「特に見返す必要なし」など、子どもが見てわかるようにラベルを貼っておく。
この一手間で、将来、感情に左右されずに手放せるようになります。

高級老人ホームの近くで、トランクルームのビジネスをしたら儲かるんじゃない?って思ってるんですよ。
『ご依頼があれば、○日以内に取り出してお届けします』
ってしたら、普通のトランクルームよりちょっと高額でも需要がありそうだし、ぶっちゃけ「アレを取り出して!」っていう依頼なんて、ほぼ来なそうです😅
一緒に片付けておくことの意味
親と一緒に片付けておくと、
「これはいらないよね」と簡単に思えたモノも、
親が亡くなってしまった後では、手が止まるようになります。
全部が“思い出”になってしまって、
結局なにも手放せなくなる。
そうならないためにも、元気なうちに、
“今使っているもの”と“なんとなく持っているもの”の分類を一緒にしておくことが大切です。
まず最初にやるべきは「自分の私物撤去」
実家を片付けたいなら、まずは自分の荷物から。
実家に自分のものが残っている状態で「片付けてよ」は、説得力がありません。
実家を物置代わりにしている子ども世代、けっこう多いです。
まずは、自分の荷物を完全に引き上げるところからスタート。


実家の片付けは「安全確保」から
高齢の親にとって、家の中にモノがあることは“転倒リスク”そのもの。
片付け=捨てさせることではなく、まずは床にモノを置かない=安全に暮らせることが大事。
動線上の安全性を第一に考えましょう。


配置は無理に変えない
「こっちの方が動線的に便利だよ」と思っても、
何十年も染みついた習慣を変えるのは、意外とストレスになります。
親の暮らしに寄り添うなら、便利さより安心感。
動線を変えることよりも、つまずかないように・物が落ちないように整えることを優先して。
おわりに|実家の片付けは、親孝行でもある
捨てるのが苦手な親。
でも、子どもと一緒なら、少しずつ“分ける”ことはできます。
• 思い出の品は飾る
• 捨てられないモノはひとまずまとめて収納ケースへ
• 床は安全に
• モノより人の気持ちを優先して
片付けは、家を整えるだけじゃありません。
“家族の関係”も整える作業です。
ぜひ、親が元気なうちに。
お盆に帰省した時にでも、一緒に片付けを始めてみてください。